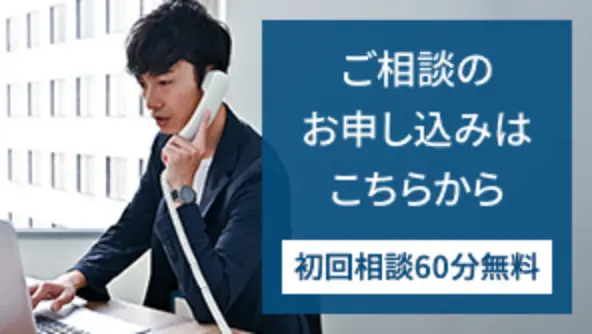迷惑な患者を診療拒否するための基準を弁護士が事例で解説

- クレームばかりつける患者の診療・診察を断りたい。
- 患者がGoogleクチコミで、当院のスタッフの誹謗中傷を行った。今後の診療はお断りしたい。
- 未払診療費が発生している患者の診療を拒否したい。
- スタッフに暴言を吐く、強く当たるなどした患者の来院を拒否したい。
- 患者に恋愛のアプローチをされて困っている。患者と距離を置きたいので診療を断りたい。
医師法には、正当な事由がなければ診療を拒んではいけないという応招義務(医師法19条、歯科医師法19条)があるため、問題がある患者の診療も拒否しにくいです。
この記事では、迷惑な患者を診療拒否するための基準やポイントを弁護士が解説します。
目次
1.診療は原則拒否できない!?応招義務について解説
病院・クリニックと患者の契約関係
患者が病院・クリニックに診療を依頼して、病院・クリニックが受諾する行為は、準委任契約の関係にあります。
準委任契約とは、法律行為以外の業務を依頼する場合の契約で、民法のルールが適用されます。民法では、契約を誰とするのかは自由です。
つまり、診療行為も病院と患者の双方の合意のもとで成立するものなので、病院・クリニックはクレーマーや迷惑な患者の診療を自由に拒否できるのが民法のルールです。
応招義務の内容
しかし、医師法・歯科医師法には、「正当な事由」がないと診察治療の求めを拒否してはいけないこと(応招義務)が記載されています。
医師法
第19条1項 診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
歯科医師法
第19条1項 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
医師法や歯科医師法は、医師が国に対して負担する公法上の義務です。
医師の応招義務違反に刑事罰も規定はされていません。
しかし、医師法に違反すると、医師免許に対する行政処分はあり得ます。
また、応招義務違反によって患者に損害が発生した場合は、病院・クリニックが患者から損害請求を受ける可能性があります。
結論:診療を拒否する正当な事由がない場合は診療を受けるべき
民法のルールで誰と契約(診療行為)するかは自由といっても、応招義務に違反することはリスクがあります。
そのため、診療行為を拒否する正当な事由がない限りは患者からの診療行為は受けるべきといえます。
2.診療を拒否できる「正当な事由」についての解説
では、どのようなケースで診療を拒否できる「正当な事由」があるのでしょうか?
「正当な事由」について、法律に細かい説明はありません。
厚生労働省医政局長の通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(医政発 1225 第4号令和元年12月25日)が参考となります。
通知には次のとおり記載があります。
このほか、医療機関相互の機能分化・連携や医療の高度化・専門化等による医療提供体制の変化や勤務医の勤務環境への配慮の観点から、次に掲げる事項も重要な考慮要素であること。
- 診療を求められたのが、診療時間(医療機関として診療を提供することが予定されている時間)・勤務時間(医師・歯科医師が医療機関において勤務医として診療を提供することが予定されている時間)内であるか、それとも診療時間外・勤務時間外であるか
- 患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係
そのため、診療拒否の正当な理由の有無は、緊急性を軸に検討します。
緊急性が高いケースの場合
病状の深刻な救急患者の場合は緊急性が高く、緊急対応が必要です。病状の深刻な救急患者のケースでは、診療時間内かどうかで分けて考えます。
診療時間内・勤務時間内の場合
緊急性の高い患者の診療拒否は原則としてできません。 しかし、医療機関・医師の専門性、診察能力、医療提供の可能性、設備の状況、他の医療機関による医療提供の代替可能性などを踏まえて事実上診療が不可能といえる場合は診療しないことに正当な理由があります。
診療時間外・勤務時間外の場合
診療時間外であっても、緊急性の高い患者の応急処置をとることが望ましいです。
しかし、診療をしなかったからといって、行政上の処分や民事上の損害賠償責任を負うことは原則としてありません。
緊急性が高くないケースの場合
病状の安定している患者は緊急性が高くないので、緊急性が高いケースと比べて診療拒否できる範囲が広がります。診療時間内かどうかで分けて説明します。
診療時間内・勤務時間内の場合
患者の求めに応じて診療を行うことが原則です。
しかし、次のような要素を考慮して診療を拒否できるケースもあります。
- 医療機関や医師の専門性・診察能力
- 患者に対する医療提供の可能性や設備の状況
- 他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)
- 患者と医療機関や医師との信頼関係
たとえば、クリニックの設備状況や医師の専門性の観点から、適切な診療を提供することが難しいケースもあります。
この場合は、クリニックでの継続診療はお断りの上で、連携をしている地域の総合医療機関を紹介することも正当な理由があるといえます。
診療時間外・勤務時間外の場合
受診や診療をお断りしても問題ないです。
診療時間内の受診の案内や他に診察可能な医療機関の紹介等の対応を行うとより親切です。
3.診療拒否に正当な理由があると判断された事例
診療拒否が裁判で争われたケースで、拒否に正当な理由があると判断された事例を紹介します。
事例1:患者から交際を申し込まれていると考え診療を拒否した事例(令和4年3月10日東京地方裁判所判決)
事案の概要
- 患者は、医師が診療を拒否等したことを理由に損害賠償請求を行った。
- 患者は医師に対して、高級紅茶ティーバッグ、クリスマスカード、クリスマスプレゼント等を渡して、「義理チョコではありません。」などと記載されたメッセージとともに手作りのお菓子等を渡していた。
- 医師は患者から交際を申し込まれたと思い、距離を置いた方がよいと考えて患者の診療を拒否した。
裁判所の判断
- 医師による診療拒否が不法行為に当たるか否かは、医師法19条1項の趣旨を踏まえて社会通念に照らして判断されるべきであり、具体的には、①緊急の診療の必要性の有無、②他の医療機関による診療可能性の有無、③診療拒否の理由の正当性の有無等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。
- 患者の傷害は、右手切創であり、紹介されたクリニックで直ちに縫合処置が実施されなかったことに照らせば、同傷害について緊急の診療の必要性があったとは認められない。
- 右手切創に対する縫合処置は、他の医療機関によっても行うことができるから、他の医療機関による診療可能性がなかったとも認められない。
- 医師が診療拒否した理由(患者からのアプローチの事情)も踏まえると、診療拒否の理由には正当性があったといえる。
弁護士の解説
この事例では、緊急性、代替診療の可能性、診療拒否をした理由などを踏まえて、診療拒否には正当な理由があると判断しました。
患者の病状が右手切創であり、緊急性は高くなかったこと、他の医療機関で処置が可能なこと、患者から医師へのアプローチがあり、医師として距離を置こうと考えた経緯などを踏まえて診療拒否の正当な理由があると判断しています。
緊急性が高くないケースでは、比較的緩やかに診療拒否の正当な理由が認められています。
事例2:患者の迷惑行為を理由に診療拒否した事例(令和5年4月26日札幌地方裁判所判決)
事案の概要
- 患者(女性)の搬送後に、医師は問診を行い、心エコー検査を行うことを説明したところ、「なぜ男性医師がやる必要があるのですか。信じられない。看護師さんの業務範囲じゃないんですか。」と大声を出して激高するなどして心エコー検査を激しく拒絶した。
- 女性看護師が心電図検査を行ったが、同検査では異常は認められなかった。
- ベッド移動のために、患者に声を掛けた男性看護師に対し、「大声を出さないでください。医療者の方が上なんですか。」などと激高した。
- 患者は点滴しないといわれたことに対して、「採血もしないで、点滴はしないと言われても納得できない、ここを動かない、帰らない、今すぐ点滴をしてください」など興奮した状態となっていた。
裁判所の判断
- 患者の状況を考えると冷静な対応を求めることができないことは明らかであり、医師や病院に対する著しい迷惑行為になっていた。
- 治療を行うために必要な医師と患者の信頼関係を築くことはできないと判断してそれ以上の診療を拒絶したことは応招義務の趣旨を考えても相当である。
- よって、医師の診療拒絶に違法な点はなく、不法行為は成立しない。
弁護士の解説
この事例では、患者が医師や看護師に悪態をついて、病院や他の患者の迷惑になっている状況でした。検査結果としても異常はなく、緊急性が高くないケースです。
緊急性が高くないケースでは、診察能力や他の医療機関等による医療提供の可能性、患者と医療機関や医師との信頼関係が重視されます。
この事例では、次のような点を考慮して診療拒否を正当と判断しているように思います。
① 緊急性
検査結果に異常はなく、緊急性は高くないこと
② 診察能力の観点
患者の言動が精神疾患に起因している可能性があり、病院側で適切に対応できない事情があったこと
③ 医療の代替可能性
精神疾患を診ることができる他の病院があること
④ 信頼関係
患者の言動が病院に対して著しい迷惑行為となっており、患者は興奮しており、信頼関係を築くことが困難な状態であったこと
4.診療拒否に正当な事由がないとされた事例
診療拒否が裁判で争われたケースで、拒否に正当な理由がないと判断された事例を紹介します。
事例1:救急車で搬送された患者の受入れ拒否に損害賠償責任が認定された事例(神戸地方裁判所平成4年6月30日判決)
事案の概要
- 患者は神戸市で交通事故に遭い、両側肺挫傷・右気管支断裂の傷害を負った。
- 消防は、神戸市の病院に搬送依頼を行ったものの、脳外科医と整形外科医が不在であるため対応できないとの返答を受けて(実際は宅直)、隣接の西宮市の病院に搬送された。
- 西宮市の病院でただちに患者の応急処置・手術が行われたが、呼吸不全により死亡。
- 患者の相続人らは、神戸市の病院の診療拒否に正当事由はないとして損害賠償請求。
裁判所の判断
- 応招義務は公法上の義務なので、医師が診療を拒否した場合でも直ちに民事上の責任に結び付くものではない。
- しかし、医師が診療を拒否して患者に損害を与えた場合は、医師に過失があるという一応の推定がなされ、診療拒否の正当事由に該当する具体的事実を主張立証しない限り医師は患者の被った損害を賠償すべき責任を負う。
- 病院側は、脳外科医と整形外科医が宅直で在院しなかったことを正当事由として主張している。しかし、外科専門医師が夜間救急担当医師として在院しており、患者を受け入れても医療の提供は可能であり、診療拒否は正当事由にならない。
- 患者は、医師が正当な理由を有さない限りその求めた診療を拒否されることがなく診療を受け得るとの法的利益を有する。その利益を侵害したことで精神的苦痛を被った。
- 結論として、病院側に150万円の賠償責任を認定。
弁護士の解説
この事例は、患者が両側肺挫傷・右気管支断裂の傷害を負っており、緊急性が極めて高い状況でした。
そのため、診療拒否は原則としてできません。
診療拒否が正当化される可能性があるのは、医療提供の可能性、医療の代替可能性などを踏まえて事実上診療が不可能な場合のみです。
この裁判事例では、脳外科医と整形外科医が宅直で在院しなかったとしても外科専門医師が夜間救急担当医師として在院しており、患者を受け入れて医療の提供が可能であったと認定しています。
そのため、事実上診療が不可能な場合ではなく、診療拒否に正当な理由はないと判断しました。
緊急性が高い患者の場合は、処置が可能な医師がいる場合は診療拒否をすると違法となる可能性が高いといえます。
事例2: 満床を理由とした受入拒否に損害賠償責任が認定された事例(千葉地方裁判所昭和61年7月25日判決)
事案の概要
- 患者(1歳)は診療所で気管支炎ないし肺炎との診断を受けて、君津市内の病院へ搬送を依頼。
- 搬送先の病院で、満床により入院できないと受入を拒否。
- 消防からの再三にわたる受入要請も拒否。消防は1、2時間の搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院の医師が診察、右搬送に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出した。
- 千葉市内の診療所に収容されたが、呼吸循環不全症状が改善せず、気管支肺炎により死亡するに至った。
裁判所の判断
1. 病院の診療義務と拒否事由について
- 病院は医師と同様に診療義務を負っている。
- 診療拒否が認められる「正当な事由」とは、原則として医師の不在または病気等により事実上診療が不可能である場合をいう。診療を求める患者の病状、診療を求められた医師または病院の人的・物的能力、代替医療施設の存否等の具体的事情によっては、ベッド満床が正当事由に当たる可能性もある。
2. 本件で診療拒否の正当な理由がないこと
以下の事情を踏まえるとベッド満床を理由とする診療拒否には正当な事由はない。
- 搬送された時間帯は小児科の担当医は3名おり、外来患者の受付中であった。
- 君津市、木更津市、袖ケ浦町には小児科の専門医がいてしかも小児科の入院設備のある病院は搬送された病院以外になかった。
- 同病院の小児科の病棟のベッド数は、6床だが、以前は同じ病室に12、13床のベッドを入れて使用していた。
- 仮にベッドが満床でも、救急室か外来のベッドで診察及び点滴などの応急の治療を行い、ベッドが空くのを待つという対応を取ることも可能であった。
3. 結論
結論として、財産的損害(逸失利益)・精神的損害として、病院側に1395万円の賠償責任を認定
弁護士の解説
患者が1歳と幼く、病状から緊急性が高い事案でした。
病院側の主張は、ベッドが満床で受入困難だったというものです。
裁判所は一般論としてベッドの満床が診療拒否の正当な理由になる可能性があることは認めつつも、具体的な状況(患者の重篤な病状、近隣に適切な医療機関がなかったこと、診療提供の可能性)などを踏まえると、多少無理をしてでも受け入れるべきであったと判断したものといえます。
仮に、患者の病状が重くなければ、違った判断もあり得たかもしれません。
患者の病状を踏まえた緊急性が診療拒否できるかの最も重要な要素です。患者の病状が重く、緊急性が高い事案では診療拒否できるケースは限られます。
5. インターネット上で患者が誹謗中傷を行った場合は診療拒否ができるか
次のような経験はございませんか?
- 患者がクリニックにクレームをつける。
- その直後にGoogleクチコミに悪いと評価、クチコミが投稿される。
- 投稿された内容は事実無根の内容、もしくは実際の事実関係を歪曲した内容で真実とは言い難い内容であった。
病院やクリニックの対応に不満を抱いた患者がGoogleクチコミに投稿をするケースはよくあります。しかも、Googleクチコミに投稿してもなお来院される患者もいます。
私もクリニックからGoogleクチコミの相談を数多く受けてきました。では、このような患者の診療拒否はできるのでしょうか?
安易な決めつけ、診療拒否はリスクがあります
Googleクチコミの内容から、投稿した患者を推測できることはあります。
しかし、安易な決めつけや診療拒否はリスクがあります。
Googleクチコミは匿名で行われるケースがほとんどです。投稿内容から患者を推測できても、本当にその患者といえるのかを証拠をもって特定することは難しいです。
安易に投稿者だと決めつけ、診療拒否すると、患者からの苦情や新たな書き込み、損害賠償請求をされるリスクがあります。
そのため、投稿者の特定と診療拒否は慎重に判断する必要があります。
クチコミが名誉毀損等にあたる場合は診療拒否できる可能性があります
クチコミが名誉毀損にあたる内容の場合は、患者とクリニック・病院との信頼関係の構築が難しいものとして診療拒否できる可能性があります。
しかし、あくまでも診療拒否に正当理由があるかは総合判断です。次のような要素を考慮のうえで、診療拒否するかどうかを慎重に判断しましょう。
- 患者の病状、緊急対応が必要か否か
- 代替可能な医療機関があるか
- 投稿内容の悪質性
- 投稿内容に虚偽事実が含まれているか
- 投稿内容が病院・クリニックの社会的信用を低下させるものか。またその程度
- 投稿内容が法的に違法となる可能性が高いか
投稿内容が法的に違法となる可能性が高いかどうか等の判断は難しいです。誹謗中傷に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
6. 診療費未払の患者の診療拒否をできるか
次のような患者はいらっしゃいませんか?
- 保険証を忘れた患者を診察
- 次回以降の診察の際も保険証を持参されずに、保険組合に医療費の請求ができない
- しかし、患者は繰り返し診察をご希望
- 治療費の未払いも発生
厚生労働省医政局長の通知の記載
厚生労働省医政局長の通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(医政発 1225 第4号令和元年12月25日)には、次のとおり記載されています。
しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。具体的には、保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないが、医学的な治療を要さない自由診療において支払い能力を有さない患者を診療しないこと等は正当化される。
また、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もある。
悪質な診療報酬未払の患者は診療拒否できる可能性があります
厚生労働省医政局長の通知の記載だけをみると、医療費未払のみで診療拒絶するのは難しいようにも読めます。
しかし、緊急性もなく、治療費の不払いを繰り返す患者は悪意があるといってもよいと思います。
診療拒否が正当化されるかは、緊急性、医療提供の代替可能性、患者と医療機関等の信頼関係などを総合的に考慮して判断されます。
そのため、患者の病状、緊急性、患者と病院との信頼関係、代替可能な病院があるかなどを個別具体的に判断のうえで診療を拒否するかを判断する必要があります。
7. まとめ:診療拒否をしてもよいかは悩ましいケースが多いです。迷惑な患者の対応で悩まれた場合は弁護士にご相談ください。
- 患者と病院の関係は準委任契約なので、民法のルールでは診療をお断りすることは問題ないです。
- しかし、医師法・歯科医師法に応招義務があります。そのため、正当な理由なく診療拒否することはリスクがあります。
- 診療拒否に正当な理由があるかどうかは、緊急性、診療時間の内外、信頼関係、診療能力、代替可能性などを踏まえて判断されます。
- 患者の病状が重く、緊急対応が必要な場合は原則として診療拒否はできません。
- 緊急性が高くない場合は、病院と患者との信頼関係などを考慮のうえで正当な理由があるのかを柔軟に判断します。ピックアップした裁判例をご参照ください。
無料相談実施中

- 監修者
- よつば総合法律事務所
辻 悠祐