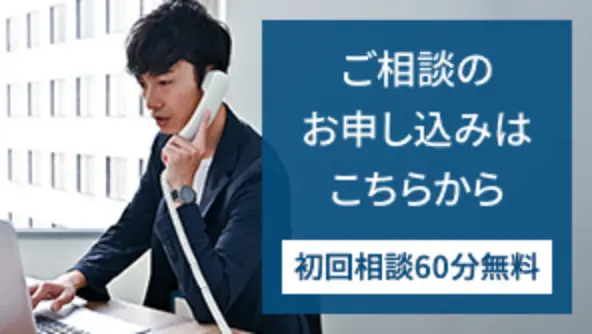クリニックや医療機関が注意すべき広告表示について弁護士が解説

医療機関の皆様、次のようなお悩みはございませんか?
- クリニックを宣伝するために、看板・チラシなどを考えていますが、広告できる範囲に制限があるのか知りたいです。
- 医療機関のウェブサイトを作成・改定中です。ウェブサイトの表示で禁止されていることがあれば知りたいです。
- インフルエンサーにクチコミを依頼したいと考えていますが何か問題はありますか?
広告規制には、景品表示法という法律があります。また、景品表示法の一般的な規制のほかに、医療機関には医療法等の独自の広告規制があります。
この記事では、医療機関の皆様が注意すべき広告表示について弁護士が解説します。
目次
1. 景品表示法による広告規制
景品表示法は、消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。具体的には、優良誤認表示の禁止と有利誤認表示の禁止の2つがあります。
優良誤認表示(5条1号)の禁止
優良誤認表示を禁止する景品表示法5条1号では、次のとおり以下の3つを規制の対象としています。
① 内容について、実際のものよりも著しく優良であるとの表示
例 カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示した場合
② 内容について、他の競争事業者よりも著しく優良であると示す表示
例 「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた。
景品表示法5条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
① 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
有利誤認表示(5条2号)の禁止
有利誤認表示を禁止する景品表示法5条2号では、次のとおり以下の2つを規制の対象としています。
① 取引条件について実際のものよりも取引の相手に著しく有利であると誤認される表示
例 当選者の100人だけが割安料金で契約できる旨表示していたが、実際には、応募者全員を当選とし、全員に同じ料金で契約させていた場合
② 取引条件について他の競争事業者よりも取引の相手に著しく有利であると誤認される表示
例 「他社商品の2倍の内容量です」と表示していたが、実際には、他社と同程度の内容量にすぎなかった。
景品表示法5条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
② 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
その他不当表示 (5条3号)の禁止
景品表示法5条3号では、優良誤認表示の禁止、有利誤認表示の禁止以外にも考えられる不当表示について内閣総理大臣に指定する権限を与えています。
現在は、以下の内容が景品表示法5条3号に基づく不当表示と指定されている内容です。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和48年公取委告示第4号)
- 商品の原産国に関する不当な表示(昭和48年公取委告示第34号)
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55年公取委告示第13号)
- 不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年公取委告示第14号)
- おとり広告に関する表示(平成5年公取委告示第17号)
- 有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公取委告示第3号)
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年内閣府告示第19号)
医療機関が特に注意しないといけないのは、⑦一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示の規制です。
ステルスマーケティング規制として、患者に対してGoogleクチコミを依頼するケースでも違反事例が出ています。別記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
医療法人やクリニックのGoogleクチコミで、ステマ規制にあたらないための注意点3選違反した場合のペナルティ
景品表示法の不当表示違反となった場合は、行為の差止め、再発防止措置の実施、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を措置命令として行うことができます(景品表示法7条1項)。
措置命令に違反した場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの刑事罰を受ける可能性もあります(景品表示法46条1項)。
優良誤認表示の禁止、有利誤認表示の禁止に違反している場合は課徴金納付命令を受ける可能性もあります(景品表示法8条1項)。
2. 医療法による広告規制
医療は人の生命や身体に関わるサービスです。そこで、利用者を保護するために、通常の広告規制より厳しい制約が課されています。
規制対象となる「広告」の意味
次の①②のいずれの要件を満たすものが広告だと判断されます。
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
- 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
チラシ、パンフレット、ポスター、看板、ホームページなどは一般的に上記①②の要件を満たすため「広告」に該当します。
患者に広告と気づかれないように行われるステルスマーケティングも「広告」に該当します。たとえば、クリニックが報酬を支払いインフルエンサーに治療内容や治療効果についてSNSで投稿してもらう例が考えられます。
そのほか、Googleクチコミ依頼のケースでもステルスマーケティングと判断される可能性があるので注意が必要です。
医療広告が可能な範囲(原則)
医療法では次のとおり、広告が可能な範囲が定められています(医療法6条の5第3項)。つまり、チラシなどで広告を出す際は以下の項目に限られるのが原則です。
- 医師又は歯科医師である旨
- 診療科名
- 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
- 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
- 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
- 第5条の2第1項の認定を受けた医師である場合には、その旨
- 地域医療連携推進法人の参加病院等である場合には、その旨
- 入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
- 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
- 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
- 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
- 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第6条の4第3項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
- 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
- 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
- その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
ウェブサイトの広告範囲
ウェブサイトなどは、次の要件を満たすことで上記の内容以外の広告も可能です(医療法施行規則1条の9の2)。これを広告可能事項の限定の解除といいます。
共通要件
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること。
自由診療の広告の場合は以下の要件も加算
- ③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。
- ④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。
クリニックや病院が作成したウェブサイトでは、患者が自ら求めて検索することになるので①の要件を満たします。
対して、バナー広告の場合は、求めていなくても表示されるので①の要件は満たさず広告可能事項の限定解除はされません。
問い合わせ先については、電話番号等をウェブサイトの分かりやすい箇所に記載しておけば②の要件との関係で問題ありません。
以上のように、クリニックで作成したウェブサイトは広告可能事項の限定が解除されているケースが多いため、チラシなどに比べて広告の自由度は高いです。
禁止されている広告
病院やクリニックのウェブサイトでは、広告可能事項の限定解除要件を満たすことが多いです。
しかし、ウェブサイトでの広告も以下の内容の規制がある点は要注意です。
- 虚偽広告の禁止(医療法6条の5第1項)
- 比較優良広告の禁止(医療法6条の5第2項1号)
- 誇大広告の禁止(医療法6条の5第2項2号)
- 公序良俗違反の広告(医療法6条の5第2項3号) 例:わいせつな写真を使用した広告
- 治療等の内容・効果の体験談(医療法施行規則1条の9第1号)
- 誤認のおそれのあるビフォーアフター写真(医療法施行規則1条の9第2号)
① 虚偽広告の禁止
医療法6条の5第1項では、「虚偽の広告をしてはならない。」と定めがあります。
医療広告ガイドラインでは、以下のような広告を違反事例としてあげています。
- 絶対安全な手術です!
- どんなに難しい症例でも必ず成功します
- 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
手術で絶対に安全、必ず成功する等は医学上あり得ないので虚偽広告として扱われます。
また、データの根拠を明確にせず、データの結果のみを示す広告や意図的に調査結果を誘導するなどして適正なデータでない場合は虚偽広告として扱われます。
② 比較優良広告の禁止
「他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告」も医療法で禁止されています。
医療広告ガイドラインでは、以下のような広告を違反事例としてあげています。
- 肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
- 当院は県内一の医師数を誇ります。
- 本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
- 著名人も当院で治療を受けております。
「日本一」「No.1」「最高」等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当します。
著名人との関連性を強調することも、患者に対して医療機関が著しく優れていると誤認されるおそれのある表現のため比較優良広告として取り扱われます。
③ 誇大広告の禁止
「誇大な広告」も医療法で禁止されています。
誇大広告とは、必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味します。
医療広告ガイドラインでは、以下のような広告を違反事例としてあげています。
知事の許可を取得した病院です!(「許可」を強調表示する事例)
法における当然の義務であり、知事の許可を得たことをことさらに強調して広告し、あたかも特別な許可を得た病院であるかの誤認を与える場合には、誇大広告として扱う
医師数○名(○年○月現在)
示された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として扱うこと
「○○手術は効果が高く、おすすめです。」
科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するものは、誇大広告として取り扱うべきであること
比較的安全な手術です。
何と比較して安全であるか不明であり、誇大広告として扱うべきであること。
④ 公序良俗違反の広告
「公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告」も禁止されています。わいせつな画像な映像、残虐な画像や映像などの広告が該当します。
⑤ 治療等の内容・効果の体験談
「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならない」と定められており、治療等の内容・効果の体験談の広告は禁止されています。
治療の体験談は、個々の患者の状態によって異なります。体験談の投稿は他の患者に誤認を与えるおそれがあるため禁止されています。
しかし、患者が自発的にSNSや口コミサイトで治療の内容・効果の体験談を投稿することまでは禁止されていません。
このようなケースでは、医療機関の利益を目的に投稿が行われているわけではなく、誘因性が欠けるため医療機関の広告にはあたりません。
他方で、クリニックが患者に対して経済的な便宜を図るなどして高評価の口コミ依頼をする場合は、誘因性が認められるとして違法な広告となる可能性があります。
⑥ 誤認のおそれのあるビフォーアフター写真
「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならない」と定められており、誤認のおそれのあるビフォーアフター写真の広告は禁止されています。
個々の患者の状態等により治療結果は変わる可能性があることを踏まえて、誤認のおそれのある写真の広告は禁止されています。
禁止の対象となっているのは誤認のおそれのあるビフォーアフター写真の広告です。
術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合はビフォーアフター写真の広告も許されます。
違反した場合のペナルティ
医療法の広告規制違反が疑われるケースでは、医療機関に対して、任意の調査、報告命令、立ち入り検査などの措置が取られることになります(医療法6条の8第1項)。
広告違反を発見した場合は、通常まずは行政指導により広告の中止や内容の是正を求めることになります。
行政指導に従わない場合や違反を繰り返すなど悪質な事例の場合は、広告の中止命令や是正命令が行われます(医療法6条の8第2項)。
命令に従わない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます(医療法87条3号)。
さらに悪質な場合は医療機関の開設許可の取り消しの可能性もあります。
3. 医薬品医療機器等法による広告規制
広告規制内容
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)でも、以下のとおり広告の規制があります。
- 医薬品・医療機器等の名称や効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止
- 承認前の医薬品・医療機器について、名称、効能・効果、性能等についての広告禁止
違反した場合のペナルティ
違反広告を行ったケースでは、広告の中止や再発防止措置などの是正勧告や措置命令を行うことができます(薬機法72条の5第1項)。
また、虚偽・誇大広告を行った事業者に対しては課徴金納付命令があります(薬機法75条の5の2)。
刑事罰もあり、虚偽・誇大広告を行ったケースや承認前の医療品等の広告を行った場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金のどちらかまたは両方が科されます(薬機法85条4号、5号)。
薬機法85条4. 健康増進法による広告規制
広告規制内容
健康増進法は、食品として販売する物に関して、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をしたり、著しく人を誤認させるような表示をすることが禁止されています(誇大表示の禁止)。
健康増進法65条1項違反した場合のペナルティ
誇大表示の違反をしているケースで、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあるケースで是正勧告を行うことができます(健康増進法66条1項)。
是正勧告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは勧告に係る措置をとるべきことを命令することができます(健康増進法66条2項)。
この命令に従わない場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます(健康増進法71条)。
健康増進法71条5. 医療機関が広告で注意すべき点3選
ポイント1:各種法令やガイドラインに違反していないか確認をする
医療や医薬品等の広告は各種法令やガイドラインによる規制が多いです。
ウェブサイトを作成する段階や広告を検討する段階で各種法令やガイドラインに違反していないか、法令遵守しているのかチェックを行うことが重要です。
ポイント2:経済上の便宜を図ってクチコミ投稿を依頼しない
経済上の対価を支払い、患者やインフルエンサーにクチコミ投稿の依頼をすることはステルスマーケティングに該当して景品表示法に違反する可能性があります。
また、医療法の禁止広告(治療の内容・効果の体験談、比較優良広告)に違反していると判断される可能性もあります。
そのため、経済上の便宜を図って患者やインフルエンサーなどの第三者にクチコミ投稿を依頼することは控えたほうがよいです。
ポイント3:ウェブサイトに広告禁止の内容が含まれていないか確認する
医療法では広告禁止事項が多いです。
広告可能事項の限定の解除の要件を満たしているか、また広告が禁止されている内容が含まれていないかをウェブサイト公開前にチェックすることが重要です。
まとめ:医療機関の広告は制限が多く悩む点が多いです。疑問点がある方は弁護士にご相談ください。
医療機関の広告では悩ましい点が多いです。
患者にクチコミ投稿を依頼する行為も一定の場合は広告と評価される可能性があります。
医療機関の広告やキャンペーンなどが法令に違反していないか等お悩みの点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
無料相談実施中

- 監修者
- よつば総合法律事務所
辻 悠祐